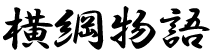豊昇龍第74代横綱へ昇進
令和7年初場所において、12勝3敗で幕内最高優勝を飾った大関豊昇龍に対して日本相撲協会は、1月29日に国技館内で春場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、第74代横綱昇進を正式に決定しました。
その後、東京都台東区の立浪部屋では横綱昇進の伝達式が行われ、「横綱の名を汚さぬよう、気魄一閃(きはくいっせん)の精神で精進いたします」と大関昇進時と同じ口上で、横綱への決意を豊昇龍は改めて述べたそうです。
新横綱の誕生と言えばまだ記憶に新しい、白鵬との全勝決戦を行い横綱昇進を果たした2021年名古屋場所後の照ノ富士以来となり、外国出身力士としては初の昇進となった曙から8人目。モンゴル出身では豊昇龍の叔父である朝青龍、白鵬、日馬富士、鶴竜、照ノ富士に次いで6人目の横綱となりました。
ちなみに昇進速度をみてみると、初土俵から所要42場所での昇進となり、年6場所制となった1958年以降では初土俵から数えると6番目のスピード昇進。 初場所では長く一人横綱を勤めていた照ノ富士が3日目に引退を表明しましたが、この豊昇龍の昇進によって、平成5年初場所以来の横綱空位という事態を避けることが出来ました。
いよいよ明治神宮での奉納土俵入り。新横綱豊昇龍のデビューまでカウントダウンに入りました。
豊昇龍の横綱昇進は妥当なのか?
横綱審議委員会では満場一致の昇進だった一方で、今回の昇進に対して好角家内では賛否両論があることもまた否めません。
以前にも書きましたが、横綱昇進の条件は 「2場所連続優勝それに準ずる成績」となっています。
豊昇龍の直近2場所の成績を見てみると、「九州場所が13勝2敗の準優勝」そして「初場所が12勝3敗での優勝」。
綱取り場所の序盤でよく使われるキーワード「レベルの高い優勝」。この基準を考えれば、たしかに色々と意見が分かれるかと思いますが、「連続優勝に準ずる成績」という観点だけから見れば「昇進の基準」はクリアしているという見方も十分にできます。
しかし今回の昇進はそこ(直近2場所)だけではなく、九州場所よりもさらに前の秋場所の8勝7敗、もっと言えば名古屋場所も二桁に届かない9勝4敗2休。この辺りの成績に注目が集まっています。
たしかに、豊昇龍がもしも横綱だったと仮定すると、この成績では及第点には遠く及ばず、秋場所に関しては途中休場の可能性さえある成績です。
下記は以前にも記載しましたが、平成以降に誕生した横綱の「昇進直前3場所」の成績です。
旭富士:8勝7敗、14勝1敗(優勝)、14勝1敗 (優勝)-36勝
曙:9勝6敗、14勝1敗(優勝)、13勝2敗(優勝)-36勝
貴乃花:11勝4敗、全勝優勝、全勝優勝-41勝
若乃花(三代目):10勝5敗、14勝1敗(優勝) 、12勝3敗(優勝)-36勝
武蔵丸:8勝7敗、13勝2敗(優勝)、13勝2敗(優勝) -34勝
朝青龍:10勝5敗、14勝1敗(優勝)、 14勝1敗(優勝) -38勝
白鵬:10勝5敗、13勝2敗(優勝)、全勝優勝 -38勝
日馬富士:8勝7敗、全勝優勝、全勝優勝 -38勝
鶴竜:9勝6敗、14勝1敗(同点)、14勝1敗(優勝) -37勝
稀勢の里:10勝5敗、12勝3敗、14勝1敗(優勝) -36勝
照ノ富士:12勝3敗(優勝)、12勝3敗(優勝)、14勝1敗 -38勝
豊昇龍:8勝7敗、13勝2敗、12勝3敗(優勝)-33勝
※同点:優勝決定戦で敗退
2場所連続優勝をしていない力士としては、鶴竜と稀勢の里の二人もいますが、鶴竜は2場所前が優勝同点、いわゆる「レベルの高い」であり、稀勢の里は3場所続けて少なくとも二桁勝利は挙げており合計で36勝、しかもこの時点でかなりのシルバーコレクター状態と安定感はありました。
それに比べて豊昇龍はというと、優勝1回で計33勝と、2場所連続の大勝ちで大関昇進を果たす位の成績と言われても仕方ない数字となっています。
このように数字上だけで見てみると、今回の昇進を不安視する声にも納得がいきます。
相撲協会の思惑
歴史をさかのぼって見てみると、、、今回の豊昇龍並みの成績を上げたにも関わらず横綱昇進を果たせなかった例は幾つかあり、私の記憶でも下記2例は特に印象に残っています。貴乃花に関しては殆んど話題にすらならなかったと思います。
魁皇:11勝4敗、13勝2敗(優勝)、12勝3敗(次点)-36勝
貴乃花:11勝4敗、14勝1敗(優勝)、13勝2敗(同点)-38勝
何故なのか?
これまで何度か横綱昇進について紹介してきた中で「その時代の空気感」という表現を使用してきましたが、今回はまさにこのケース。番付上の問題が大きな要因となっています。
例えば現在仮に二人の横綱が存在していたならば、場所前から「レベルの高い優勝」が必須となっており、2敗した時点で「綱取り」は絶望視されたはずです。12勝3敗の優勝では「横綱昇進」ではなく、「来場所は綱取り挑戦」という機運が高まった場所後になっていたはずです。
しかし、初場所の照ノ富士引退により「横綱不在」となってしまい、興行としては最大の目玉を失ってしまう危機が迫った相撲協会。
財団法人設立100周年を迎え、ロンドンやパリ公演も控えています。ここは是が非でも「新横綱」は誕生させたかったはず。
最大の昇進理由は「気迫」
今回の横綱昇進に対して賛否が上るのは、恐らくこういった背景を加味してのものであることは間違いありません。
確かに多少強引な成績での昇進なのは明らかで、関係者の中でも全員が納得の昇進にはなっていないことと思っています。
とはいえ、果たして新横綱豊昇龍の誕生は、相撲協会の後押しがあったからこそ成り立ったのでしょうか?
今場所終盤まで昇進に首をかしげていた好角家達の中には、千秋楽をはじめとした終盤戦で見せる豊昇龍の気迫に、「横綱」のそれを見たファンもいたのではないでしょうか?
豊昇龍の持つ「雰囲気」や「気迫」といったオーラこそが今回の昇進を最も後押ししたと私は思っています。
初土俵以来初めて負け越した幕下2枚目の7番相撲。
負けた後土俵を叩いて悔しがった気持ちこそが、今なおライバル視された同期達を大きく引き離して出世した大きな力となっているはずです。
「相撲協会の思惑で昇進した」「豊昇龍が可哀そう」「これから維持していくのが大変」
15年前に土俵を去った横綱は、この程度では済まないもっと激しい声を浴びせられる中で勝ち続けました。
そのDNAを引き継ぐ新横綱。春場所は賜杯を手にして、全員を黙らせてやろうじゃないか。
頑張れ豊昇龍。
横綱昇進おめでとうございます。