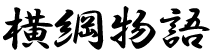スポーツとしての相撲論
久々に相撲関連の書籍を紹介したいと思います。
今回は先日出版されたばかりの本、
「スポーツとしての相撲論」です。
こちらの著者”西尾克洋さん”ですが「幕下相撲の知られざる世界」という
ブログを書いているライターの方で、今回初の書籍発行となりました。
私もこうして相撲ブログを書いていますが、元々ネットでこちらのブログを発見し、自分も書いてみようかと思ったのがきっかけです。
全部で30の質問に対して西尾さんが丁寧に回答していくという内容になっているのですが、一言感想を言わせて頂くと、非常にわかりやすく丁寧でやはり文章がうまいなあ・・・と、相撲以外の部分で感心してしまいました笑
こんな人に読んでほしい
特に読んでほしいのは以下の3グループに該当する相撲ファン!
1.相撲ファン初心者
細かい技とかルールは分からないけど、
「気がつくと最近なんか相撲中継見てるよね」
「●●がお気に入り」
「場所ごとに言える力士名が増えてきた」
そろそろ趣味に相撲観戦と書こうか迷っている方。
奇数月の夕方、結局18時まで相撲中継を見てしまいます。
2.スー女
推し力士や箱推ししている部屋に対する愛情や情熱は、相撲オタクの私では到底足元に及ばない彼女たち。技や歴史なんかより、現地情報や力士の状態、生活・趣味なんかに関しては興味津々。終盤戦、3勝3敗同士の推し対決に引き分けがないことを常に悲しんでいます。
3.もっと相撲を深掘りしたいファン・再発見したいファン
相撲はよく見ていて比較的詳しいけど、もっと深く知りたいそこの貴方。
相撲中継の取り組み間に流れる豆知識を最近は妙に楽しんでいます。
この観点で読んでほしい
土俵上・取り組みに関して
本の中では技術面・相性・立ち合いの重要性・力士の体重差・メンタル面など、取り組みに関することをスポーツ的な観点で説明しているので、来場所以降テレビを通して見る取り組み内容に面白さが増すのではないかと思います。
以前に比べるとお兄ちゃんの解説など、スポーツ的な観点が入った説明も増えてきましたが、技術的な視点も入れると大相撲中継が数段面白くなってきます。
相撲界の側面に関する情報
力士の給与・年寄株や一門制度・年齢・病気や怪我・公傷制度・入門条件など、普段相撲を見ている中で疑問に思うことはもちろん、相撲界における様々な疑問に回答しています。土俵上での取り組みや勝敗、力士個人だけを見ていると改めて知る機会が少ないことなどを知ると、より大相撲全体に興味が増し、さらなるマニアへの第一歩になるような気がします笑
現状の相撲界について
現在の相撲界に関して、少し前の時代を振り返りながら説明しています。
朝青龍時代から、もしくは相撲人気が再燃したのちに相撲ファンになった人にとっては、その前の時代と比べながら語る現在の相撲界は新鮮に映るかもしれません。
平成の相撲ブーム世代として願うこと
私は西尾さんと同世代になるので、若貴ブーム時のフィーバーが社会現象だったことをリアルタイムで経験しています。現在も相撲ブームとは言われてはいますが、入門者数が過去最大だったかつての時代に比べると雲泥の差です。
今回改めて色々と勉強になりましたが、文中にあった以下の一文は非常に重い意味があると思います。大相撲が少しでも底辺拡大が行われ魅力ある身近な競技になっていって欲しいと思っています。
「今すぐ対策を実施しても入門者については15年あまり現状維持もしくは悪化するしかないのです」
ちなみに貴乃花ファンの方は、貴乃花と相撲ブームに関して言及している部分をぜひ読んで欲しいと思います。
非常に共感しました。